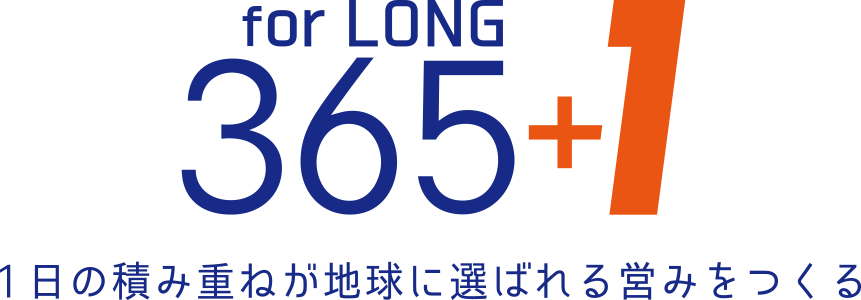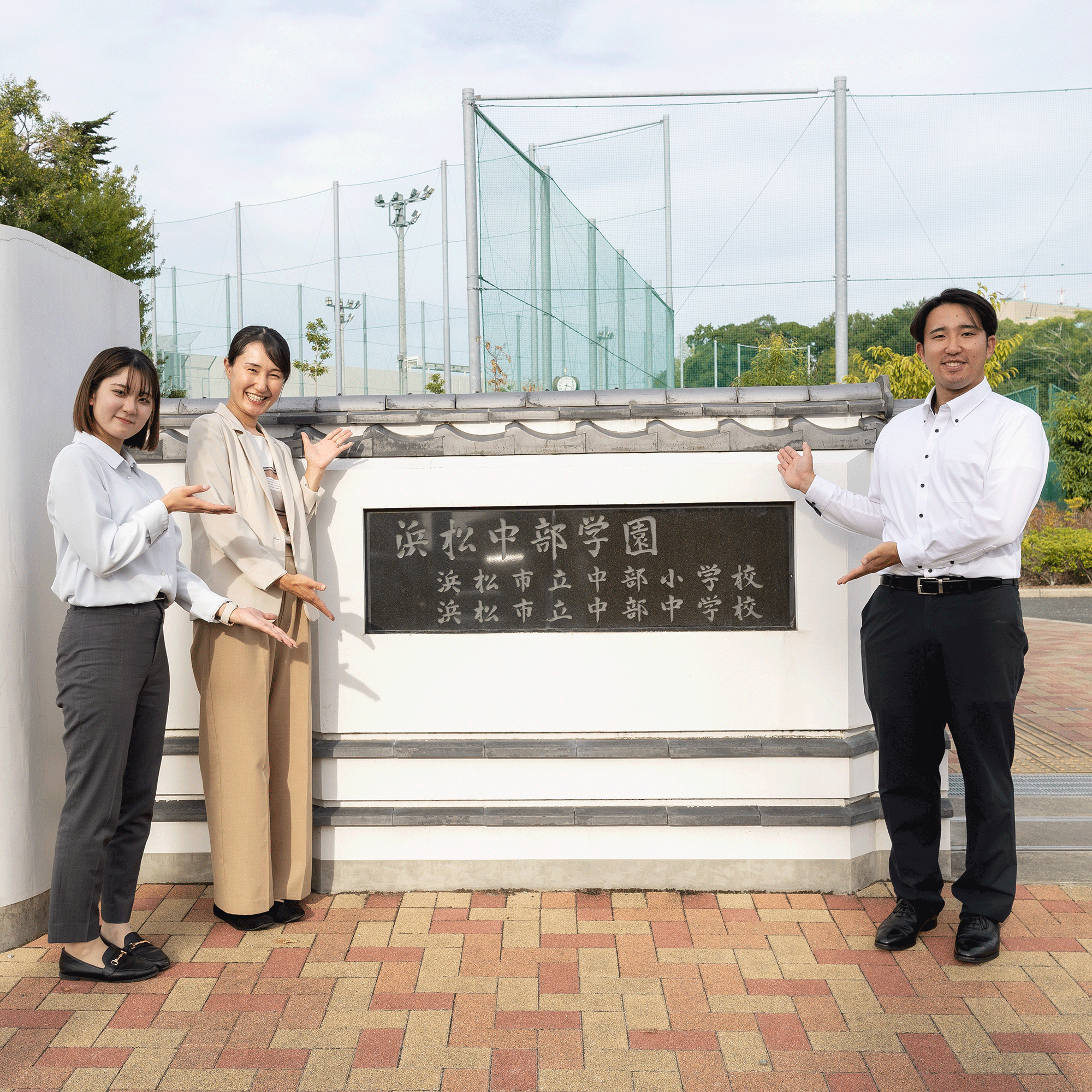浜松発クラフトビールのプロジェクト「HOP to BEER」に参画! ビールを通じた地域活性化に地元企業らが意欲

- クラフトビールづくりから生まれる、新しい地域コミュニティ
- 「ビール」が「ビール好き」を呼び、人の輪が広がっていく
- 人との出会いがもたらす、社会貢献と自己の成長



建築以外の側面でも街を盛り上げたい
 取材班
取材班浜松発のクラフトビール「HOP to BEER」は、昨年から始まったプロジェクトだと聞いています。まずは髙林さん、プロジェクトの概要を教えてください。
 髙林さん
髙林さんその名の通り、ホップからビールをつくろうというプロジェクトです。私が代表を務める株式会社HACKが企画したもので、法人・個人に関係なく参加していただけます。まずは初年度とあり、僕たちの会社に近しい人に声を掛けさせていただき、9つの会社と個人では9人から申し込みがありました。ビールが好きの方、地域コミュニティに興味がある方、CSR活動をしている企業など、応募理由はさまざまです。
 取材班
取材班申し込みのあった企業と個人にホップの苗を分けて、実際に育ててもらったと聞いています。
 髙林さん
髙林さんはい、春先に植えて7・8月に育つイメージです。身近な野菜だと、ゴーヤに近いですね。みなさんに収穫してもらった実は、最終的に浜松市内にあるブルワリーにお願いして、クラフトビールにしてもらいました。
 取材班
取材班ご説明、ありがとうございます! でも、アイジースタイルハウスは、どうしてこのプロジェクトに参画したのでしょうか。
 佐原さん
佐原さん弊社とお付き合いのある材木店の方がプロジェクトに参加していて、「アイジーさんもどう?」と声を掛けていただいたのがきっかけです。地元の活性化には兼ねてから興味がありましたし、「JAPAN WOOD PROJECT」のような建築の側面とは違った視点から街を盛り上げられるのなら、ぜひ、協力させていただきたいなと思ったんです。あとは、弊社の高木さんがビールが大好きで(笑)。
 高木さん
高木さんはい、ビール大好きな高木です(笑)。昨年4月に開かれたキックオフミーティングにも参加して、ホップの育て方などを教えてもらいました。その時に、実際にホップの苗も分けてもらったのが印象深いです。
 髙林さん
髙林さんみなさん、ビール好きという共通点があったので、初対面でも盛り上がっていましたね。


初めてのホップ栽培に四苦八苦
 取材班
取材班ホップを育てるのは、難しいのでしょうか。
 髙林さん
髙林さんホップって、冷涼なところで育ちやすいんです。日本では、北海道や岩手が主な産地になっていて。なので、暑い浜松でホップが無事に育つのかは心配でもありました。ほかにも、ツルが6メートルほど伸びるので、育成環境をどう整えるかなどの懸念もあり……。結果的には、みなさんが愛情を持って育ててくれたので、無事に収穫までこぎ着けることができました。長野にある農家で10株ほど育ててもらったのも含めて、4キログラム強の収穫になりました。
 取材班
取材班4キログラム強のホップで、どれくらいの量のビールがつくれるのでしょうか。
 髙林さん
髙林さん300リットルのタンクでビールをつくったのですが、それに必要なホップの量は4キログラム強ではとても足りないとのことで、ペレットホップという加工済みのホップを足してつくりました。フレッシュホップだけで300リットルのビールをつくるのは、狂気の沙汰だそうです。
 取材班
取材班そうなんですね……! アイジースタイルハウスでは、誰がホップを育てたんですか?
 佐原さん
佐原さん植物やお酒が好きな人が多いこともあり、みんなが協力してくれました。肥料を与え、水やりをして。ツルが伸びるためのヒモを、オフィスの屋上まで準備するのが大変でした。あとは、真夏の熱波が……。お盆休み中の法人は苦労したんじゃないですか?
 髙林さん
髙林さんそうなんです。水やりをしないと、一気に枯れてしまうので。
 高木さん
高木さん佐原さん、お盆休み中にも出社して水やりしていましたもんね。ありがとうございました。今年は自動散水できる環境を整えられるといいな、なんて思っています。
 佐原さん
佐原さんそんなこともあり、弊社の分のホップは育つのが遅くなってしまい、お渡しする予定だった期間には間に合わなかったんです。それでも、小さく実ってくれたホップを目にした時は、感慨深い気持ちになりました。よくぞ、育ってくれたと。


 取材班
取材班ホップの収穫を経てクラフトビールが醸造され、昨年11月にはお披露目会があったそうですね。
 髙林さん
髙林さん「アーバンファーミングデイ」というイベントに合わせて、お披露目しました。新川モールで育てているキノコを収穫して、その場で調理して食べたり、都市型農業を始めるにはどうすればいいかという講演会もありました。ビールのお味はいかがでしたか?

 佐原さん
佐原さん自分は特別お酒が好きというわけじゃないんですけど、おいしかったです。
 高木さん
高木さんめちゃくちゃおいしかったですよ。正式な商品名は「YARAMA IPA」と言うんですけど、そのアイピーエーというのがホップの香りが強いビールの種類で。とってもフルーティーな香りがしました。
 取材班
取材班「ヤラマ〜」という名前には、どんな意味があるのでしょうか。
 髙林さん
髙林さんクラフトビールは「〜アイピーエー」という名前が多くて、名づけは自由なんです。そこで、浜松の方言である「やらまいか」(=やってみようか、の意)と掛けてみました。完成したビールは、参加してくださった法人・個人のみなさんにおすそ分けさせていただきました。昨年は一般販売するほどの量をつくれなかったのですが、今年は一般販売できるくらいのタンクでつくってみたいと考えています。
 佐原さん
佐原さん今年の2月には、いただいたビールをオーナーさまに振る舞う機会がありました。そのなかには、浜松で収穫した芋でポテトチップスをつくっている経営者の方もいたのですが「自分も(今年のビールづくりに)参加します」と仰っていて、新たな広がりを感じられる場となりました。


 取材班
取材班髙林さんは「HOP to BEER」というプロジェクトを通じて、どんな未来を形づくっていきたいですか?
 髙林さん
髙林さんビールというツールを用いて、「浜松でおもしろいことをしているな」と多くの人が集まるきっかけをまずはつくりたいです。HACKは、まちづくりの会社ですので、そこから新しい地域コミュニティを生み出していければ。地域社会に参加する糸口になれれば、うれしいです。そうして、街に住む人々の人生がより豊かになっていく、お手伝いをできれば幸いです。
 取材班
取材班とっても、すてきです! アイジースタイルハウスとしては、HACKとどのような化学反応を起こしていきたいですか?
 佐原さん
佐原さん大前提として、仕事というのは「人の役に立つこと」だと思っていて。なので、地域社会を活性化できるのであれば、今年以降も喜んで参画させていただきたいなと考えています。社会的に価値あることをすればするほど、社員のエンゲージも上がっていきますし、いろいろな人との出会いは自身の成長につながります。いいことづくしのプロジェクトなんですよ。
 取材班
取材班人の輪が広がっていくと、いいですよね。
 佐原さん
佐原さんそうなんです。アイジースタイルハウスは「衣食住」の「住」の部分に重きを置いていますが、「住」から派生した豊かな暮らしのなかに「YARAMA IPA」があるのは、とてもおもしろいなと思っていて。アイジースタイルハウスを媒介して、オーナーさまにも「HOP to BEER」の輪が広まっていけば理想的です。
 高木さん
高木さんオーナーさまと一緒にホップを収穫して、街を賑わせるビールをつくっているんだと体感していただければ、なおのこと、うれしいですよね。そして、浜松のことをもっと好きになってもらえれば、私たちが参画している意味もより深まっていくのだと思います。

材木店の方の何気ない一言から始まった、「HOP to BEER」への参画。そして、オーナーさまへの新たな広がり。人と人がつながっていく瞬間を感じたのが、取材での印象深い出来事でした。
このプロジェクトに参画している人の共通点は、「新しいことをおもしろがる人」であり、「街を愛している人」。クラフトビールが、そんな人たちの呼び水となっているのでしょう。そして、この記事を読んでいるあなたも、きっと、その一員です。「やらまいか」と気軽に輪の中に入ってみては、いかがでしょうか。